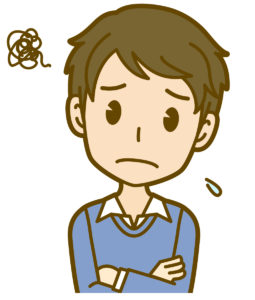
という疑問をもってググったあなたへ
はじめまして。
陽翔(ヨーショウ)といいます。私も大学を退学しています。
いきなりですが結論から。
結論:ハローワークを使うべきか?
- 大学中退者はハローワークを使うべきではない
- 首都圏や地方都市から遠い人はハローワークも併用してみると良い
私たち大学中退者にとっては、
ハローワークを使う意味はほぼゼロです。
その理由はこちら。
ハローワークをおすすめしない5つの理由
とは言っても、大学中退後の就活を自力で何とかするのはキツいですよね・・・。
正解:じゃ、どうすればいいのか?
退学後の就職活動は、
- 大学中退者向けの就職支援サービスを利用する
が正解です。
少なくとも「思考停止してハローワーク」ではなく、大学中退者向けの就職支援サービスとハローワークを比較検討し、そのメリットとデメリットを知ってから決めるべきです。
そもそもハローワークを使う事が目的ではなく、退学後の就職を乗り越えることが目的ですからね。
さて、深堀りしてきます。
この記事を読み終えると、大学中退後の就職の成功率が格段にアップすること間違いなしです。
ロードマップで解説
中退後を生きるヒントをロードマップで解説。
-

大学中退者の就職から人生逆転までのロードマップ【仕事・お金・人生~何もあきらめたくない~】
続きを見る
» 大学中退者の就職から人生逆転までのロードマップ【仕事・お金・人生~何も諦めたくない~】
※本記事のリンクには広告が含まれる場合があります。
ハローワークの特徴


まずはハローワークについて、ざっと知っておきましょう。
公式ホームページ
ハローワークの特徴
ハローワークの正式名称は「公共職業安定所」。「職安」って呼ぶ人も。
ハローワークは国の機関です。
厚生労働省管轄で設立は1947年と歴史も長く、60代以降の方であれば「仕事探し=ハローワーク」と考える人が圧倒的に多いですね。
ちなみにハローワークには大きく2つの機能があります。実は職業紹介だけではないんです。
- 職業紹介・転職相談
- 雇用保険事業
この先、会社を辞めて失業保険をもらう時にはハローワークにお世話になるのですが、今は知らなくていいです。
そして肝心の1つ目の「就職紹介・転職相談」機能を問題視する声があるようです。(後ほど説明します。)
ハローワークのメリット
ハローワークのメリットはとにかくその「数」です。
- 基本的に日本全国どこもでサービスが受けられる。(拠点数が多い)
- 日本全国の非常に多くの求人を扱っている。(求人数が多い)
とにかく拠点の数と求人の数が多い。
民間のエージェントなどは拠点は首都圏や地方都市に限られ、求人も全国をカバーしているわけではありません。
冒頭でもお伝えしたとおりで、首都圏や地方都市以外で仕事を探す場合、ハローワークも併用するのはありだと思います。
でもハローワークにはデメリットも多いです。特に私たち大学中退者にとっては。次の章で詳しく解説しますね。
大学中退後の就職でハローワークをおすすめしない5つの理由


結論、私たち大学中退者にとって、ハローワークのメリットはほぼゼロです。
そして言葉を選ばずにぶっちゃけます。
大学中退後の就職はそんなに甘くはない。
ハローワークに行ったところで乗り越えることはできないですよ。
ハローワークをおすすめしない5つ理由
ハローワークを通じての就職率が低すぎるから
ハローワークを通じての就職・転職の割合は全国で2割、首都圏では1割未満という情報があります。
80%の人はハローワーク以外から仕事を見つけているという現実があり、その点が問題として見られている一面もあるようです。この事実は知っておくべきです。
独立行政法人「労働政策研究・研修機構」に興味深いレポートがあったので一部抜粋しておきます。(が、全部読む必要はないです)
その一方で民間企業のある調査は,大都市圏の転職者について入職経路を詳細に調べているが,その結果(首都圏1都4県・2000 年・単数回答上位5位まで。無回答 8.8%を除く)によると,1家族や友人・知人(29.7%),2新聞広告(17.4%),3ポスター・チラシ・タウン誌等(11.5%),4求人情報誌(11.4%),5ハローワーク(8.5%)となっている。この結果によれば,地域共同体が崩壊しているといわれる大都市においても入職経路のトップは縁故(家族,友人,知人)によるものであり,労働需給調整機関(情報提供・斡旋機関等)だけをとってみると全体の約4割が,チラシ,新聞,求人情報誌等の「求人広告」となっている。他方,上記の通り,ハローワークは 8.5%のシェアにすぎない。ハローワークと競合関係にある民間企業の調査データではあるが,首都圏では1割にも満たない(つまり「1 割未満職安」)のが現状となっている。
「ハローワーク(公共職業安定所)の役割は何か?」より抜粋


大学中退者の就職はただでさえ不利。
とにかく就職率が少しでも高い相手に相談しないと、どうにもならないです。だからハローワークはおすすめできないんです。
ハローワークの職員さんはキャリアアドバイザーではないから
民間の転職エージェントのキャリアアドバイザーと比較してしまうと、ハローワークの職員の転職相談の質は高くは無いと感じるでしょう。
担当の人の中には「いかにもお役所仕事」って人もいました。
1つ1つの企業や求人の内容を把握しているという感じではなく、求人票にある情報を読んでいるだけに思えました。


一方、民間の転職エージェントのキャリアアドバイザーは実際に企業の人事担当と密に連絡を取っていて、求人票には表現されない例えば企業のカルチャーなどに細やかに情報を把握していることが多いです。
そもそもハローワークとは、職員があなたにあった求人を探して提案してくれるというシステムではないです。
ハローワークでは基本的に自分で求人を探すことになります。
なんというか、役所での手続きに似た感覚なんですよね。
- まずは、番号札を取って待ち、呼ばれたら窓口に行って手続きをする。
- そして、PCで自分自身で求人を探す。
- 何となくこれかな、というのを見つけてまた窓口に行ってエントリーの手続きをする。
こんな感じです。
求人の量が多いから仕方ない部分もあるんですが、ぶっちゃけ就職の相談に乗ってもらっている感覚はないです。
これじゃ、大学中退者の不利な状況を突破していくなんて、まず無理ですよ・・・。
ハローワークは質より量だから
実際にハローワークを利用した私の感想ですが、質の低い求人に結構な割合で遭遇します。
ハローワークは国の機関であるからか企業側からフィーを取ることができない。
つまり企業は無料で気軽に求人を出すことができるからか、結果として、求人の質にバラつきが出てしまうと考えれます。
そしてハローワークの職員が、求人の質を1つずつ精査したり、情報の鮮度を保ったり、その企業の実態の確認を行うことは事実上不可能なんでしょう。
全国をカバーする大量の求人を扱うこと自体がハローワークの1つの目的でもあるはずなので、もうこれは仕方ないと言うか。
ハローワークの求人はブラックが多いとも言われる理由はこのあたりにあるかと思います。
ブラック企業に搾取される。
これは大学中退者の就職の失敗の代表例です。なんとしてでも回避しないとダメです。その後の人生がどうにもなりません。
ハローワークは大学中退者に特化したサービスではないから
とは言え、もちろん、中にはまともな求人もあります。
ですが、私たち大学中退者がこのまともな求人にめぐり合い、内定までこぎつけることは困難を極めます。
大学中退者が就職先を探すには、最低限このような求人を探し当てないと話になりません。
- 学歴不問
- 社会人経験ゼロでもOK
- 大学中退に理解がある
- ブラック企業を避ける
そして、このような求人に数多くエントリーした先に内定獲得があります。
ですが、
- 大学中退者向けの求人を専門に扱うでもない
- 職員さんが相談に乗ってくれるわけでもない
- 基本的にPCで自分で探す
という状況で中退者がエントリー可能な求人をたくさん見つけることができますでしょうか?
まず無理ですって。
つまり、ハローワークは大学中退者に特化したサービスではないので、中退者にとってメリットがないのです。
というか、ハローワークからしてみたら
そもそも、ウチは中退者向けの就職支援サービスをやってるわけじゃないからな、そんなこと言われても困る・・・
ってことなんですよね、きっと。
はい。ハローワークが大学中退者向けに何かをやってくれる、ということは一切ありません。
中退者の就職は甘くない!ハローワークでは乗り越えられないから
そもそも、私たち大学中退者の就職は甘くないですよ。
退学後に正社員として就職できる割合は34%程度というデータがあります。残り66%の中退者は低賃金の非正規雇用として生涯を終えるということです。
このハードルを乗り越えるには、大学中退者が少しでも有利になるものは何でもフル活用しないと本当に厳しいです。
そもそも、多くの人が「就職支援=ハローワーク」と考える理由分かりますか?
それは、昔は就職支援はハローワークしかなかったからです。つまりハローワークが良い悪いの議論はさておき、ハローワークしか選べなかったから。
長いあいだハローワークは就職支援の代名詞だった。この印象だけが令和の現代においても続いてしまっているんです。
でも「就職支援=ハローワーク」だったのは昭和時代の話ですよ。
今は多くの就職支援サービスが存在し、大学中退者にメリットがある質の高い支援サービスはたくさん登場しています。
ハローワークしかなかった昔に比べて選択の幅は桁違いに増えています。
それでも思考停止でハローワークですか?
スマホや携帯がある時代なのに、固定電話や公衆電話しか使わないのと同じですよ。
昔はハローワークしかなかった。でも現代は大学中退者に特化した就職支援サービスが登場しています。
あなたはどうしますか?
ちなみに私は大学中退者したら人生終わりだ、
なんてことを言いたのではなりません。
大学退学しても活用できるものをフル活用すれば、就職できるしその先に人生もどうにでもなります。


だから絶望する必要はありません。
ですが、思考停止して「仕事探し=ハローワーク」だと難しいですよ。
ハードな中退後の就職を乗り越えるには、少なくとも大学中退者向けの就職支援サービスとハローワークを比較検討し、そのメリットとデメリットを知ってから決めるべきです。
もし、中退者向けの就職支援サービスを詳しく知らないなら、この先を読んだら控えめに言っても人生変わりますよ。
大学中退後の就職ではハローワークではく「中退者向けの就職支援サービス」を利用すべき


大学中退者向けの就職支援サービスとは、一般的な転職エージェントサービスではなく、その名の通り大学中退者やフリーターに特化した就職支援サービスを提供しています。
人材業界で最大手のリクルートが提供する「就職Shop![]()
![]()
ハローワークとの最大の違いは、間違いなく「その質の高さ」です。マジで違います。
その特徴の違いを比べてみました。
| 比較ポイント | 大学中退者向け 就職支援サービス | ハローワーク | ||
| 大学中退者 へ特化 | ◎ | ・大学中退者に特化したサービス ・就職講座も無料提供 ・書類審査なしの求人が多い | ✖ | ・大学中退者に特化していない ・大学中退者に特にメリットはない |
| 就職率 | ◎ | ・80%以上 | △ | ・全国で2割 ・首都圏だと1割未満 |
| 求人の質 | ◎ | ・学歴不問 ・社会人経験なしOK ・大学中退者への理解 ・ブラック企業を徹底排除 ・1社1社の実態をしっかり把握 ・厳選した求人を扱う | △ | ・情報鮮度が古いものも ・ブラック企業も混ざっている ・企業側も無料(厳選されていない) |
| キャリア相談 の質 | ◎ | ・キャリア相談のプロ ・大学中退者就職のプロ ・企業や求人を良く知る | △ | ・職員さんはプロではない ・求人が膨大で把握は無理 |
| 利用料金 | ◎ | ・無料 | ◎ | ・無料 |
| 拠点数 求人数 | 〇 | ・首都圏・地方都市が中心 | ◎ | ・拠点は日本全国(膨大) ・求人も日本全国をカバー(膨大) |
※横スクロールします。
ま、一目瞭然ですよね。
詳しくはこの記事にまとめているので、ぜひ確認してみてください。
-



大学中退経験者が就職エージェントのすべてを徹底解説【就職成功への全12のポイント】
続きを見る
» 大学中退経験者が就職エージェントのすべてを徹底解説【就職成功への全12のポイント】
ここでは中退者向けの就職支援サービスの特に知って欲しいメリット3点を簡単に解説します。
大学中退者に特化したサービスを提供
まずは何より「大学中退者に特化」している点が最大のメリットです。
実際に中退後の就職活動をしたら分かりますが、大学中退者は就職したくてもほぼ相手にされません。
まず多くの求人の条件が”大卒以上”とされています。
そして学歴の条件が無い企業に書類を送っても、無視されるか「残念ながら今回は見送りとさせていただきます」のラッシュとなります。
もちろん、中退者も候補者として考えてくれる企業はあるにはありますが少数派。それを自分の力で見つけていくことは困難を極めます。
数を打ちまくればどこかに引っかかる可能性はありますが、その前に心が折れてしまうでしょう。
何を隠そう私もその一人ですから。仕方なく就職を一度あきらめてフリーターになりました。(因みにフリーターは最悪の悪手です。別の記事で解説します。)
こういった大学中退者特有の就職のやりずらさをフォローしてくれるのが中退者向けの就職支援サービスです。
各社このようなメリットを打ち出しています。
もちろんすべて無料です。
もはや利用しない手はないと思います。
大学中退者が就職しやすいように無料の講座を提供
正直相当におすすめです。というか、私の時代には無かったのでうらやまし過ぎです。
大学中退者でも採用されやすい求人大学中退者特有の就職のやりづらさをサポートしてくれます。- 高卒、大学中退者の就職支援に強い
- 書類選考無し
- 学歴ではなく人物重視の企業と面接ができる
- 全て正社員求人
- 内定率だけでなく、入社後定着度も低い就業サポート
- 未経験大歓迎、就活と学習を両方サポート
求人の質の高さ
中退者向けの就職支援サービス各社は、求人の質の高さをアピールしています。こちらは一例です。
- ブラック企業を徹底的に除外
- 企業は100%取材
- 離職率・労働時間・社会保険の有無などで厳しい自社基準
- 厚生労働省委託「職業紹介優良事業者推奨事業」の職業紹介優良事業者を取得
これはわたし個人の意見ですが、
国の機能として古くから提供されている職業紹介の領域に、民間企業が後から参入してきているわけなので、そもそも規模やカバー範囲などの「数」で勝負しようとしても全く勝負にならないのでしょう。
だから、民間の就職支援サービスはその質の高さを売りにして参入。
そして今やその質の高さでハローワークの職業紹介機能のシェアを奪っているということなんですよね。
これを知りどう思いますか?
キャリアアドバイザーのサービスの質の高さ
エージェントのキャリアアドバイザーはその道のプロです。
言い方悪いですが、ハローワークの職員さんとは全く質が違います。
もちろん、ハローワークにはひとりひとりに細やかなサービスをするという機能はないので、本来比較するべきではないのです。
しかし、利用する我々求人者からすれば、就職は人生を左右する。失敗すれば死活問題になるので、相談する相手の質は何より重要じゃないですか。
エージェントのキャリアアドバイザーとは、事前のメールや電話でのやり取りから始まります。
事前に何回かやり取りをして、希望やキャリアの方向性を伝えることが可能です。少なくとも私はそのように利用します。
キャリアアドバイザーは、面談までにあなたに合った求人を数10社ピックアップして準備してくれます。
そして、その企業を提案する理由とその会社に入る為のアプローチ方法やその後のキャリアについても提案してくれます。
もちろん、提案する企業の内情まで把握している。
場合によっては、実際のそのエージェントからその企業に就職した人からも情報を集めてて、正直おすすめとか、ここはやめた方がいい、というレベルで会話が可能。
大学中退者向けの就職支援サービスを解説
-



大学中退経験者が就職エージェントのすべてを徹底解説【就職成功への全12のポイント】
続きを見る
まとめ:大学中退後の就職でハローワークを使うべきか?【目的は就活を乗り越える事です】


この記事はそろそろ終わりです。最後に簡単に振りかえりますね。
大学中退後の就職活動でハローワークを使うべきか?についての結論は、最初にもお伝えした通りです。
結論:ハローワークを使うべきか?
- 大学中退者はハローワークを使うべきではない
- 首都圏や地方都市から遠い人はハローワークも併用してみると良い
ハローワークをおすすめしない5つ理由
正解:じゃ、どうすればいいのか?
退学後の就職活動は、
- 大学中退者向けの就職支援サービスを利用する
が正解です。
少なくとも「思考停止してハローワーク」ではなく、大学中退者向けの就職支援サービスとハローワークを比較検討し、そのメリットとデメリットを知ってから決めるべきです。
中退者向けの就職支援サービスのメリット
詳しくはこちらの記事にまとめているので、ぜひ確認してみて下さい。
続きを見る


大学中退経験者が就職エージェントのすべてを徹底解説【就職成功への全12のポイント】
» 大学中退経験者が就職エージェントのすべてを徹底解説【就職成功への全12のポイント】
この記事で大学中退後に後悔しない人生をあるくヒントになれば幸いです。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
大学中退者の人生逆転ロードマップ【目次】
【ステージ1:情報収集と就活始動】
- 大学中退者の人生逆転ロードマップ全体の流れを知る
- 大学中退後の就職が厳しい理由と対策を知る
- 大学中退者が人生逆転するための就職先の選び方を知る
- 大学中退者の就職のベスト時期を知る
- 大学中退者向けの就職支援サービスを探す
【ステージ2:最初の就職をクリア】
- 就職支援サービスへ就職相談・無料研修受講
- 大学中退の理由を整理する(面接官が確認したい事を知る)
- 大学中退者だけど会ってみたいと思わせる履歴書を作成する
- 大学中退者の面接の戦い方を知る
【ステージ3:急成長できる環境へ】
- 社会人としての基礎固め
- 目的地とこの先のルートの再確認
- 第二新卒枠をフル活用する転職準備
【ステージ4:市場価値アップ】
- 急成長できる環境にてフルコミット
- キャリアを市場価値の棚卸し→必要に応じて補強
【ステージ5:収入と人生を収穫】
- 収入面で大卒者に追い付き・追い越す
- 望む人生を手に入れる
ロードマップで解説
-



大学中退者の就職から人生逆転までのロードマップ【仕事・お金・人生~何もあきらめたくない~】
続きを見る
» 大学中退者の就職から人生逆転までのロードマップ【仕事・お金・人生~何もあきらめたくない~】
