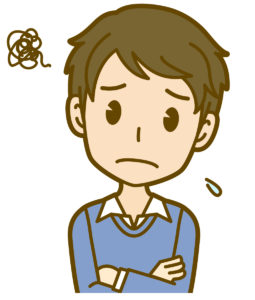
って思っていませんか?
私も大学中退後の仕事として、公務員を考えたことがあるので良くわかります。
大学中退後の進路として安定したイメージのある公務員は確かに魅力的です。しかし、そのイメージだけで公務員を選んだら後悔しますよ。
はじめまして、
陽翔 (ヨーショウ)といいます。
私は21歳の時に大学を中退しました。遠回りしつつも就職して現在は大卒者以上の収入を得ています。公務員を目指す事を真剣に考え抜きましたが、最終的に民間企業で働くことを選択しました。
ちなみに、私には公務員の親族がたくさんいるので、公務員の内部事情には詳しい方です。
公務員 or 民間企業
どっちを選ぶべきか?
この記事では、あなた自身に判断してもらうための「5つのチェックポイント」をご提示いたします。
それ以にも、公務員のメリット・デメリット、知っておくべき公務員の真実など、私が公務員を選ばなかった理由など、今後の進路を判断する材料やヒントをお届けします。
私は世の中の情報が「大学中退後に公務員=正解」に偏り過ぎていると感じます。
公務員に関する出来る限りの情報を知り、さらに他の選択肢も知った上で、フラットにどうすべきかを判断した方が良いですよ。
この記事の内容
ぜひ、最後までお付き合いください。
大学中退者でも公務員になれるのか?

答えはYes。
大学中退者でも公務員になれます。
公務員には様々な種類があり、それぞれ異なる資格や試験が必要となりますが、必ずしも大学卒業が必須ではありません。
そのため、大学中退者でも公務員を目指すことは十分可能です。
むしろ、学歴よりも試験の結果が重視される公務員試験は、大学中退者にとってハンデが少ないとも言えます。
ここでは、公務員の種類と大学中退者が公務員になる方法について詳しく説明します。
大学中退者が公務員になる方法
大学中退者が公務員になるためには、公務員試験を受け合格することが必要です。
試験は一般的に一年に一度開催され、試験科目は法律、経済、一般教養など幅広くあります。
大学中退者は高卒扱いで、大学卒業資格が必要のない試験を受けることが可能です。
専門学校や通信教育での学習が有効
公務員試験に出題される科目の勉強だけでなく、面接対策なども行います。大学中退者は専門学校への入学や通信教育を利用することで、効率的に公務員試験対策をすることができます。
志望する職種や勤務地を明確にすることも重要
次項で説明しますが、ひとことで公務員といっても色々な仕事があります。各公務員の職種や地域により試験内容や試験形態が異なるため、自分に合ったものを選択することが求められます。
公務員の3つの種類
公務員には大きく分けて国家公務員、地方公務員、国際公務員の3つの種類があります。
公務員の仕事は社会の安定と進歩に欠かせず、公正な行政や国際協力の実現に向けて重要な役割を果たしています。
国家公務員
国家公務員は、国の中央政府で働く公務員の一群です。彼らは国の行政機関や省庁で働き、法律や規制の適用、政府の政策実施、国民の福祉の向上などを担当しています。
国家公務員の役割
- 法律や政策の策定と実施
- 行政サービスの提供
- 国内外の情報収集と分析
- 国民の権利保護と社会秩序の維持
地方公務員
地方公務員は、地方自治体(市町村や都道府県)で働く公務員のことを指します。彼らは地方政府の運営や地域の発展、地方住民の利益のために様々な業務を行います。
地方公務員の役割
- 地方自治体の運営と行政業務
- 地域開発と都市計画の推進
- 教育や福祉施設の管理
- 地方税の徴収と予算管理
国際公務員
国際公務員は、国際機関や国際組織で活動する公務員のグループです。彼らは国際平和や安全、開発、人権などの分野で国際社会の利益を追求し、国家間の協力を促進します。
国際公務員の役割
- 国際法や規則の策定と遵守の監視
- 国際協力と開発プロジェクトの推進
- 平和維持活動や紛争解決の支援
- 人道支援と人権保護の促進
注意ポイント
国際公務員は多くの場合、学士号以上の学位を持っていることが要求されるので、大学中退者が目指すことは現実的ではありません。
大学中退者が受験可能な公務員試験
一般的に、公務員試験の受験資格は学歴によって限定されることはありませが、国家公務員の中級試験や上級試験など一部の試験は大学卒業が必要とされます。
下記のように大学中退者でも受験可能な試験はたくさんあります。
- 国家公務員試験(初級・準中級):
大学卒業資格は必要ありません。国民として必要な一般教養と、それぞれの職種に必要な専門知識が問われます。
- 地方公務員試験:
地方公務員試験の多くは、学歴に関係なく受験することができます。ただし、試験内容は自治体によって大きく異なります。
公務員のメリットとデメリット
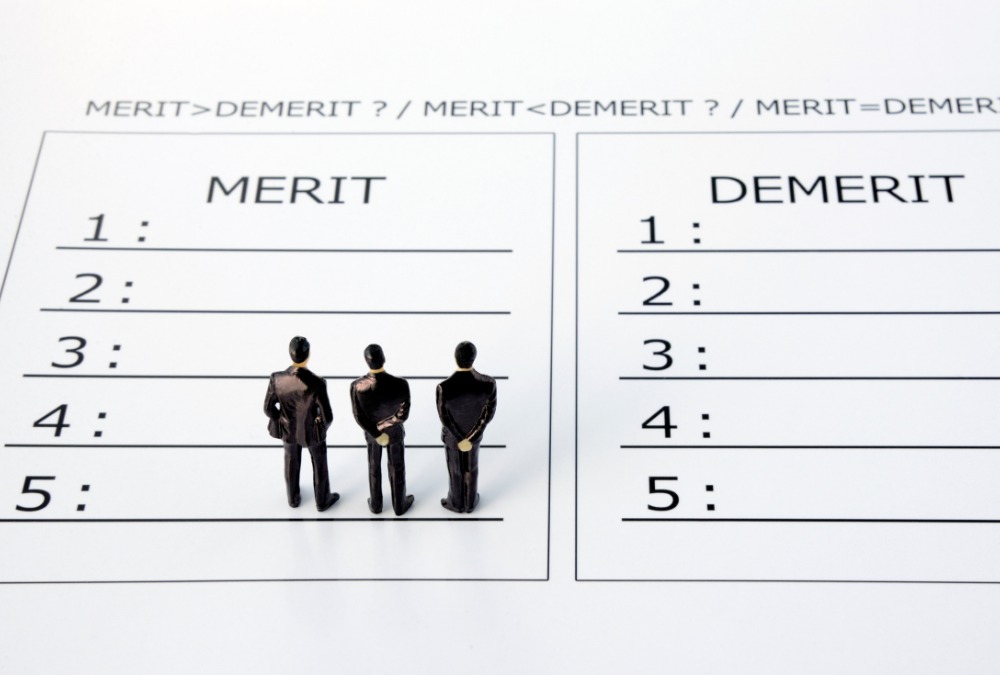
安定・安心のイメージが強い公務員ですが、もちろんデメリットもあります。
公務員のメリットとデメリット、そして公務員になって良かった人と後悔する人についてお伝えします。
公務員として働くメリット
- 安定した雇用:
公務員は安定した雇用が保証されており、経済的な安心感があります。まさに公務員として働く一番のメリットですね。
- 公平な待遇:
公務員は給与や昇進の基準が明確であり、公正な待遇が期待できます。
- ワークライフバランス:
公務員の仕事は時間外労働が少なく、休日も安定しています。ワークライフバランスを重視する人にとって、これは大きな魅力となります。
- 福利厚生:
公務員は充実した福利厚生が提供され、健康保険や退職金などの手厚い制度があります。
公務員として働くデメリット
- 給与の制約:
公務員の給与は一般的に民間企業に比べてやや低く、ボーナスなどの報酬面でのメリットは限られています。
- 厳しい規律:
公務員は厳格な規律に従う必要があり、柔軟性や自由度は制約されることがあります。
- お役所的仕事・官僚主義:
公務員の業務には煩雑な手続きや規制が存在し、決定までに時間がかかることがあります。
- 政治的な影響:
公務員は政治的な変化の影響を受けることがあり、業務内容や方針が変わることがあります。
大学中退後に公務員になって正解の人と後悔する人
大学中退後に公務員を目指す方々にとって、その選択が正解か後悔するかは個人によって異なります。
公務員になって正解の人
- 就職の安定性を重視する人:
大学中退後でも公務員として安定した雇用を得ることができ、将来の安心感を求める人にとっては正解となる場合があります。
- 公共の利益に貢献したい人:
公務員は社会的な責任を果たす役割を担い、公共の利益のために働くことができます。社会貢献に喜びを感じる人にとっては正解となるでしょう。
公務員になって後悔する人
- 個人の成長や挑戦を求める人:
公務員は一般的に働き方や組織の制約があるため、自己成長や新たな挑戦を求める人にとっては後悔の要因となる可能性があります。
- 給与や待遇面を重視する人:
公務員の給与は民間企業と比較してやや低めであり、昇給も緩やかな傾向があるため、給与や待遇面を重視する人にとっては後悔の可能性があります。
- 創造的な仕事が好きな人:
公務員の仕事は一定の規則や法律に基づいて行われるため、新しいアイデアを自由に生み出したり、創造的なアプローチをとったりする機会は限られるかもしれません。そのため、創造的な仕事が好きな人にとっては、公務員はあまり向いていないかもしれません。
- 多様なキャリアを経験したい人:
公務員は一般的に定年まで同じ職場で働くことが多いです。多様な業種や職種を経験し、幅広いスキルを身につけたいと考える人にとっては、公務員が最も適した職業であるとは言えません。
民間企業のメリットとデメリット

次に、大学中退者が民間企業で働く場合のメリットとデメリット、そして就職の考慮点をまとめました。
民間企業で働くメリット
- 高い給与:
民間企業は一般的に公共部門や非営利組織よりも高い給与を提供します。また、成果に応じたボーナスや昇進の機会もあります。
- 成果に基づく評価:
民間企業では成果や能力に基づいた評価が行われます。優れた業績を上げることで報酬やキャリアの発展が期待できます。
- 働き方の柔軟性:
民間企業では、フレキシブルな労働時間やリモートワークの選択肢があることがあります。自分のライフスタイルに合わせて働くことができます。
- イノベーションと成長の機会:
民間企業は市場競争の中で生き残るために常にイノベーションを求めます。新しいアイデアや技術を取り入れることで、自己成長やキャリアの発展が促されます。
民間企業で働くデメリット
- 高い競争:
民間企業は多くの人が求職するため、競争が激しいです。求人数に対して応募者が多いため、入社までの選考プロセスが厳しくなる場合があります。
- 長時間労働:
業界や職種によっては、長時間労働や残業が求められることがあります。仕事とプライベートのバランスを取るのが難しいこともあります。
- リストラや倒産の可能性:
必要な利益を出せなくなった民間企業は生き残るためにリストラをすることも珍しくありません。またそれでも利益が出せない場合に会社が倒産する可能性もあります。つまり、民間企業は公務員に比べて職を失う可能性が高いということです。
大学中退後に民間企業に就職して正解の人と後悔する人
大学中退後に民間企業に就職することは、人によって結果が異なります。
民間企業に就職して正解の人
- 自己成長と経験重視:
大学中退後に民間企業に就職し、実務経験を積むことで自己成長を追求する人は、正解と言えます。経験を通じて自身のスキルや知識を磨くことができ、将来のキャリアに有利になる可能性があります。
- 目標や意欲を持っている:
就職後に自身の目標を設定し、それに向かって努力する姿勢を持つ人は、公務員よりも民間企業が向いています。
民間企業に就職して後悔する人
- 大学中退のハンデを自力で何とかしようとする:
大学中退後の就職活動は大きなハンデがあります。大学中退者ありの戦い方をすれば、そのハンデを乗り越えることも可能です。しかし、誰にも頼らず自力でどうにかしようとすると、仕事内容・将来性・収入・満足度の全てにおいて、希望通りではない仕事にしかつけない可能性が高いです。
- 社会的なプレッシャーに屈する:
大学中退後に民間企業に就職することに対して、周囲や社会からのプレッシャーに屈している人は後悔する可能性があります。自身の意思ではなく、他人の期待や評価に基づいて民間企業を選択した結果、充実感ややりがいを見出せないことがあります。
- 目標や意欲が欠ける:
大学中退後に民間企業に就職しても、目標や意欲が明確でない場合は後悔することがあります。民間企業は公務員よりも実力主義の世界なので、成果が出せないと思うようなキャリアが描けず後悔する人もいます。
大学中退後の就職のハードルを乗り越えるための全てをここに書きました。必読です。
-

大学中退経験者が就職エージェントのすべてを徹底解説【就職成功への全12のポイント】
続きを見る
» 大学中退経験者が就職エージェントのすべてを徹底解説【就職成功への全12のポイント】
公務員か民間企業か?5つのチェックポイント


公務員 or 民間企業
どっちを選ぶべきか?
キャリアへの考え方や価値観、適性などは人によって異なりますので、大学中退者の全員に当てはまる解答などありません。当然です。
「あなたが」公務員を選ぶべきか、民間企業を選ぶべきか、そこの見極めをミスらないことが何より重要です。
ここでは、あなた自身に判断してもらうための「5つのチェックポイント」をご提示いたします。
自身の価値観、プライベートをどう考えるか、キャリア目標をどう考えるかを十分に検討して、最適な選択をしましょう。
自身の価値観との整合性
最初のチェックポイントは「公務員という仕事そのものに価値を見出せるかどうか」です。
そして「民間企業の利益と競争力を最優先にした価値観があっているかどうか」です。


安定・安心というメリットは魅力的ですが、これから40年以上働くその職業が、「やりたくない仕事」「価値感が合わない仕事」だったとしたら間違いなく後悔します。
公務員と民間企業では、その目的、職務内容、働き方、そして求められるスキルや能力には大きな違いがあります。
- 公務員:
社会全体の公共の利益を最優先に仕事をします。法律や規則を厳格に守り、公正かつ公平なサービスを提供します。
- 民間企業:
民間企業は利益の最大化と競争力の強化を追求します。その競争に負けた会社は淘汰され、競合他社に勝つために新しいアイディアや技術を活用した新しい会社がどんどん生まれます。民間企業の中でも価値観やカルチャーは千差万別で、選択肢の幅は非常に広いです。
給与と福利厚生
給与と福利厚生もキャリア選択において重要な要素です。
ざっくり言うと、公務員の給与は大企業の給与には及びませんが、民間企業の平均よりも少し下くらいで最底辺というわけでもありません。その代わりに終身雇用と年齢による昇給が保証されています。
公務員の給与と福利厚生
一般的に民間企業よりも低い給与水準です。その代わりに給与は一般的に安定しており、福利厚生も充実しています。そのため、生活設計が予測しやすく、安定した生活を望む人に適しています。国家公務員の様が地方公務員よりもやや高い水準になります。
民間企業の給与と福利厚生
会社の規模や業界によって平均給与は大きく異なります。また、その年の会社の業績や個人のパフォーマンスによっても給与は大きく上下します。平均的には公務員よりも高い水準が一般的ですが、就職先によっては公務員よりも低水準になる可能性あります。福利厚生も企業により異なり、最低限の福利厚生しかない企業も少なくありません。一部の企業では、業績連動のボーナスや株式オプションなど、公務員にはないインセンティブを提供することもあります。また、業界や会社によっては、有給や男性社員の育休が取りずらいカルチャーが存在することも念頭に置いておくべきです。
仕事内容とキャリアパス
公務員と民間企業でのキャリアパスは、それぞれの特性と目標によって大きく異なります。
公務員と民間企業の仕事内容とキャリアパスの一般的な特徴を整理しました。
また、現代は転職が当たり前になってきました。転職という観点でも公務員と民間企業を比較してみました。
公務員の仕事内容とキャリアパス
公務員のキャリアは、行政、法律、財政、環境、教育、警察、消防など、社会全体の運営を支える多岐にわたる分野で働くことを含む可能性があります。
公務員の具体的な仕事内容は、その職種や職務によって大きく異なります。
- 安定性:
公務員の仕事は非常に安定しています。ほとんどの公務員は終身雇用制度のもとで働いており、一度採用されると、リストラや解雇のリスクが非常に低いです。
- 昇進と成長:
公務員の昇進は主に年功序列制度に基づいています。つまり、勤務年数が長ければ長いほど、より高いポジションに昇進する可能性が高くなります。また、特定の試験をパスすることで昇進することもあります。
- 給与:
公務員の給与は、役職や経験、教育レベルなどに基づく公式の給与スケールに従っています。パフォーマンスに基づく賞与は少なく、給与の大部分は基本給と定期的な昇給によるものです。
公務員からの転職には以下の特徴があります。
- 公務員から公務員への転職:
公務員間での転職は比較的珍しいかもしれません。しかし、異なる部門や機関、地域への移動は可能です。公務員の転職は、新たな経験を得たり、異なる公共サービスの領域で働く機会を探したりする場合に行われます。通常、転職には内部の移動や試験を通じて行われ、新たな役割や地域に対する適応が必要となります。もし公務員という働き方の価値観が合わないと言う理由で転職する場合、その不満は解消されない可能性が高いです。
- 公務員から民間企業への転職:
公務員から民間企業への転職は、より高い給与、キャリアの進歩の機会、または新たな業界への興味から行われることが多いです。しかし、このタイプの転職は公務員の安定した雇用と引き換えに、業績や市場状況により影響を受けやすい職場環境に移ることを意味します。さらに、新しい企業文化や業務の速度に適応するためには時間と努力が必要となる場合があります。公務員での経験やキャリアが活かせるとしたら、政府との取引を行う企業や、公共政策に関連する仕事をする企業ですが、転職の目的と合致しているかはしっかり見定める必要があります。
民間企業の仕事内容とキャリアパス
民間企業でのキャリアは、産業、専門性、企業の規模などによって大きく異なります。
製造、販売、マーケティング、エンジニアリング、人事、財務など、様々な部門で働く機会がありますが、民間企業では新しい仕事内容が次々と生まれる変化が激しいので、ここでは一般論にとどめておきます。
- 変動性:
民間企業でのキャリアは、市場の需要と供給、企業の業績、経済環境などに大きく影響を受けます。これらの要素により、雇用の安定性や昇進の機会、給与などが変動する可能性があります。
- 昇進と成長:
民間企業では、昇進は主にパフォーマンスと業績に基づいています。個々の努力と成果が評価され、優れたパフォーマンスを示すと急速に昇進する可能性があります。また、スキルや知識を拡大するための研修や教育の機会も多く提供されます。
- 給与:
民間企業の給与は、一部が基本給で構成され、他の部分がパフォーマンスに基づくインセンティブやボーナスで構成されることが一般的です。給与は企業の業績、個々のパフォーマンス、市場の状況などによって大きく変動する可能性があります。
民間企業からの転職には以下の特徴があります。
- 民間企業から民間企業への転職:
民間企業間の転職は最も一般的なパターンで、多くの場合、新たなキャリアの機会、より高い給与、プロモーションの機会、あるいは新しい業界への興味などが動機となります。これは、経験やスキルを新たな環境に適用し、成長と発展の新たな機会を提供します。しかし、このタイプの転職は新たな企業文化や役割に適応する必要があり、競争が激しい場合があります。
- 民間企業から公務員への転職:
民間企業から公務員に転職することは、安定した雇用、一定の給与、または公共サービスへの興味を検討する人が一定数います。しかし、この転職は公務員試験に合格した上で選考プロセスを経る必要がありますので、民間企業での経験やキャリアが活かせないケースを覚悟した方が良いです。また、公務員への転職には年齢などの制限があるので、民間企業への転職に比べると選択肢の幅は相当に少なくなります。また、民間企業とは異なる公務員の文化や規則に適応する必要があります。
ワークライフバランス
ワークライフバランスは生活の質に直接影響する要素です。
ここは給与とセットで考えるべきところです。
ハードワークで高い給与を求めるなら公務員になるべきでありませんし、給与よりも安定やプライベートを重視するなら公務員もしくは、そのような民間企業を目指すべきです。
- 公務員:
公務員は定時制の場合が多く、休日もほぼ保証されています。また、有給の消化や産休・育休の取得にも積極的であることが多いです。これは育児や介護など、私生活で時間を必要とする人々にとって大きなメリットです。
- 民間企業:
民間企業では、企業によるバラツキが大きいのが特徴です。ほぼ残業がない企業もあれば、仕事の量や期限により労働時間が長くなる場合もあります。しかし、柔軟な働き方を導入している企業も増えており、在宅勤務やフレックスタイム制度を利用できる場合もあります。最近は共働き家庭が増えているので、家庭事情に寛容になってきている傾向は感じます。
安定性とリスク
最後に安定性とリスクの項目です。
安定性の高さは公務員のメリットとして誰もがイメージしますよね。
ただし、民間企業の全てが職を失うリスクが高いかというとそうでもありません。今でも終身雇用を守っている民間企業も多かったりします。
- 公務員:
公務員は、雇用の安定性が非常に高く、リストラのリスクも少ないのが特徴です。これは、経済の変動に影響を受けにくいという点で、長期的な安定を求める人に適しています。
- 民間企業:
民間企業は、ビジネスの成果や市場環境の変化により、雇用の安定性が左右されます。最悪の場合は倒産によって有無を言わさず職を失う可能性もあります。しかし、そのリスクと引き換えに、新たなビジネスチャンスや急速なキャリアアップの可能性もあります。
大学中退後に公務員を選ばなかった3つの理由


この章では「公務員になることも考えた私が、なぜ最終的に公務員を選ばなかったのか?」その3つの理由を解説いたします。
もちろん、大学中退後に公務員を目指すべきか、民間企業を目指すべきかは、人によって異なりますし、公務員がNGと言いたいわけではありません。
大学中退後に公務員を選択しかなったパターンの一例として読んでいただければと思います。
大学中退後に公務員を選ばなかった3つの理由
大学中退しても稼ぎたいという野心があったから
大学中退しても稼ぎたいと思っていました。だから公務員を選びませんでした。これが一番の理由です。因みに目標年収は1000万でした。
一般的な公務員の収入は安定しているけど少し低めです。「よっしゃ、めっちゃ働いて、めっちゃ稼ぐぜー」ってモチベーションで公務員になる人はいません。1000万プレイヤーの公務員なんて聞いたことないですし。
国家公務員のキャリア組で出世すればかなり高い年収を得ることも可能ですが、大学中退者ではキャリアと呼ばれる区分の試験を受けることすらできません。
つまり、大学中退で公務員になっても稼ぐことはできません。
大学中退したけど、稼ぎたいという野心がある人は公務員を選ぶべきではありません。
給料は民間企業の平均よりも少し下
世の中のイメージどおりの年収設定です。
公務員の給料は国民が納める税金でまかなわれています。この事実から公務員の給料設定というのは、民間企業の平均を目安に少し下に設定されているらしいです。
つまり「底辺というわけではないけど、やっぱりちょっと低め」ということです。
人の3倍働いても3倍の給料にはならない→年功序列
こちらも世の中のイメージどおりです。
公務員で人の3倍働いて3倍の給料をもらう、というような事は出来ません。もろに年功序列の世界です。
自分よりも先達の給料を抜く事は出来ませんし、昇進していくにもポストが開くのを待つ、という従来の年功序列の世界です。
転職しながらキャリアアップして年収もあげて行く→公務員ではできない
大学中退後の就職で希望するような仕事に就けるとは思っていなかったので、下積みから初めてスキルアップし、必要に応じて転職しながらキャリアアップしようと考えていました。
しかし、公務員で転職?って疑問がありました。ある区役所から別の区役所に移るのが転職?いや違うよね。それってただの異動だよね。
少なくとも別の職場に変わったからといって、給与水準や評価軸が変わるわけじゃないはずなので、転職しながらキャリアアップという戦略が取れないのです。
公務員から民間企業への転職もなくは無いですが、それであれば最初から民間企業へ入れば良くて、安定を求めて公務員になることそもそも矛盾します。
専門的なスキルが身につかないように思えたから
大学中退というハンデを背負った上で稼ごうと思ったら、学歴では勝てないわけだから、大卒者にも負けないような専門性・スキルが必要と考えていました。
一般的な公務員の仕事では専門的なスキルを身につけることは難しいです。
そもそも公務員になるとどんな仕事をするのかが全然想像できなかったんです。安易に想像できるのは「区役所とかの職員とか?」くらいの知識しかありませんでした。
稼ぐための専門的なスキルが身につくとはどうしても思えず、中退しても稼ぎたいという野心があった私には、どんな仕事をするのか?というのはすごく重要でした。
ですので、大学中退後に公務員の道を選択しませんでした。
詳しくは後述するのですが、公務員の仕事は区役所職員以外にも勿論たくさんあります。
しかし専門的なスキルがつけられる仕事に就くことはなかなか難しいです。
一般的には数年おきに異動があり、全く畑違いの仕事を転々とする、というのが一般的な公務員なのです。
大学中退という学歴のハンデを埋める為に専門的なスキルや経験を身につけたいのであれば、大学中退後に公務員を選ぶべきではないです。
都内在住なので仕事の選択肢がたくさんあったから
私は都内在住だったので仕事の選択肢はたくさんあったのです。
勿論、世間は大学中退者にはそんな甘くはなく、採用される可能性はグッと狭まりますが、それでも民間企業は星の数ほどあるので、就職活動を諦めずに頑張ればどうにかなると考えたからです。
逆に、民間企業の数が少ない地域に住んでいた場合、一定数の求人があると思われる公務員は有力な候補になったとは思います。
ここは住んでいる地域や仕事で通える地域の民間企業や求人の数で考えてみると良いと思います。
公務員のリアルを公開【割と知られてない3つの事実】


続いて一般論とは少し違う、私が実際に見聞きした公務員のリアルをお届けします。
繰り返しですが、私の近しい親族に公務員が複数人います。
身内から公務員の内部事情が漏れ聞こえてくるので外部の人間としては少し詳しいです。
その中で世の中一般的には余り知られていないけど、大学中退後に公務員を考える人が知っておくべき事実を3つ紹介いたします。
大学中退後に公務員を考える人が知っておくべき事実を3つ
さて、それぞれ、大学中退者という立場で解説を加えていきます。
注意
地方公務員の場合は地方自治体によって違いがあるようです。あくまで私が観測できる範囲で知りえた非公式な内容となります。(ですが、現役の公務員から漏れ聞こえたリアルな話となります。)
公務員は学歴が重視され、大学中退(高卒)は出世は難しい
高卒でも公務員になる事は可能ですが、出世できるのは大卒・院卒だけ。高卒で出世することは相当に難しいってご存知ですか?
国家公務員の場合、合格した試験によって「キャリア組」と「ノンキャリア組」に明確に区別されます。当然、キャリア組は出世コース、ノンキャリアは昇格できる階級に上限があります。これは割りと一般的に知られているかと思います。
そして、学歴で受けることができる試験区分が明確に区別されていて、高卒で受けられるのはノンキャリアに属する試験区分のみです。
つまり
大学中退=高卒=ノンキャリア組=出世は難しい
と学歴で明確に決まってしまいます。
地方公務員の場合は、キャリア・ノンキャリアという呼び方はしないようですが、基本的には考え方は同じだそうで、「高卒」か「大卒」かで出世できるかどうかがほぼ決まるようです。
この事実を大学中退者に当てはめて考えてみるとかなり厳しい現実があります。
私は「大学中退者は学歴が出世に影響する仕事を選ぶべきではない」と強く主張しています。
理由は、学歴が出世に影響する仕事を選ぶと、一生涯「中退の烙印」を背負うことになるからです。
公務員は学歴が出世に影響する仕事です。
因みに実力や実績でどうにかなる世界では無いそうです。ここが大学中退の選択としてかなり厳しいかなと思う点です。
私は大学中退した時点はこの事実を明確には知りませんでした。どんな仕事でも大卒の方が有利ではあると思いますが、公務員がここまで明確に区別されているとは思ってもいませんでした。
「公務員は学歴が重視されて大学中退では出世は難しい」。大学中退後に公務員を選ぶにあたり知っておくべき1つ目の事実です。
仕事が楽で毎日定時で帰宅なんかではない(そんな仕事はごく一部)
誤解を恐れずに言いますが、公務員の仕事って楽なんだろうなと思っていました。毎日定時上がりで気楽な仕事というイメージ。
本当にすいません、これは間違いでした。
公務員の仕事はそんなに楽な仕事ではないですね。前述したように公務員の仕事は多岐にわたります。職種や職場によっても違うでしょうけど、毎日定時上がりの仕事をしている人はごく一握りのようです。
そして一見楽そうに見える区役所・市役所の仕事であっても、国や地方公共団体の職員として仕事をしているのでミスは許されないというプレッシャーがあります。
楽そうだから・・・という理由で公務員を選ぶと「思っていたのと違う!」という状況になりえます。なぜ公務員になりたいのかはよく考えるべきです。
数年後ごとに異動があり、やりたい仕事を選ぶことはできない
基本的にはやりたい仕事を選ぶことはできないと考えるべきです。
ちなみに、そもそも、公務員になってどんな仕事をするのかって想像つきますか?
学校教員や区役所の職員の仕事はイメージしやすいのですが、それ以外の仕事って余り馴染みが無いですよね。
少しだけ想像しやすいように地方公務員を仕事を調べてみました。この記事は公務員の仕事を網羅する目的はないので、ごく一部の紹介ですがこんな仕事があります。
- 区役所・市役所などの職員
- 公立学校の教員
- 児童相談所の職員
- 国立・公立病院の職員
- 国立・公立図書館の司書
- 福祉関係の仕事
- 水道などのインフラ関係
- 警察や消防
私の親族は教育関連から福祉関連に異動になり、そこでも数年経つので、そろそろ別の仕事に異動になるだろうと言っています。
エンジニアという専門的な仕事をしている私の感覚では最初は理解できませんでした。
民間企業で働く私はキャリアに関して、このようなことを考え続けてきました。
- 将来的にどんな役割でどんな仕事をしていたいのか?
- そしてどらくらいの年収を得てどんなライフスタイルにしたいのか?
- そこに至る為にどんなキャリア戦略を立てるか?
しかし数年ごとに異動があり全く異なる仕事をすることが当たり前の公務員は、民間企業で働く場合とキャリア構築の考え方が全く違うのです。
そもそも「やりたい仕事にする」、「自分のキャリア構築の為に仕事を選択していく」という考え方ではなく、どんな仕事であっても「国や地方公共団体の為に働いている」という考え方が根本的にあるのです。
本当に公務員になりたいの?【不安だから公務員を選ぶのは間違い】


既にお伝えしたように、私は大学中退して公務員になるか迷いましたが、ITエンジニアの道を選びました。
正直、20数年前に公務員を選ばなくて良かった、エンジニアの道を選んで本当に良かったと思っています。
収入で全てが決まるわけじゃないですが参考までにこちらのツイートをご覧ください。
エンジニアになり人生逆転した例です。参考までに
✅21歳 年収170万
大学中退バイトエンジニア✅25歳 年収400万
派遣エンジニア✅30歳 年収600万
ITベンチャー✅35歳 年収800万
ITベンチャー管理職✅40歳 年収1100万
外資系IT管理職#駆け出しエンジニア— 陽翔@年収8桁稼ぐ外資系ITエンジニア (@engineer_yosho) January 3, 2020
大学中退のハンデを乗り越えてそこそこの人生を手に入れることが出来ました。
私の仕事に対する志向は「人の3倍仕事をして3倍収入をもらいたい」というタイプなので、明らかに公務員には向いていないのですが、それでも安定感がメリットである公務員になろうか悩みました。
理由は「大学中退後の就職が上手くいくかどうかへの不安」、「大学中退後に上手く生きていけるかどうかの不安」があったからです。
私は公務員の仕事そのものをやりたかったのではありません。
もし大学中退後の人生の不安を解消したいが為に公務員を選んでしまっていたら、100%人生を後悔していたと断言できます。
ここで改めて質問します。
本当に公務員になりたいと思っていますか?


まず、この質問をした理由を言います。「大学中退後の人生の不安だからという理由で公務員を選ぶのは間違いだから」です。
公務員という仕事を舐めちゃいけません。
そんな楽な仕事ではないです。国や地方公共団体の為に働きたいというモチベーションがないとやっていけないのではないかとさえ思います。
もう一度聞きますよ。
本当に公務員という仕事をしたいと思っていますか?
大学中退に対する不安を何とかしたい、安定したものにすがりたい、と思う気持ちは良くわかります。
しかし、そんなあなたがやるべき事は、本当はやりたいとも思わない公務員にチャレンジする事ではなく、大学中退者の人生の戦い方を知ることです。
こちらに大学中退後の人生の戦い方についてまとめた記事をご紹介いたします。
大学中退者の人生の戦い方
大学中退後の最初の就職が最初にして最大の難所です。
これを如何に乗り越えるかでその後の人生はある程度決まります。思考停止してフリーターになると危険な理由、大学中退者の就職活動・その後の人生の戦い方をまとめました。
-



大学中退経験者が就職エージェントのすべてを徹底解説【就職成功への全12のポイント】
続きを見る
-



大学中退後の就職を乗り越える【中退経験者が語るベストアンサー】
続きを見る
大学中退後にエンジニアを目指す人へ
私が人生逆転できたのはエンジニアを選んだからです。その理由と大学中退者がエンジニアになる方法をまとめました。
-



【大学中退者がエンジニアを目指す】中退者にとってベストな方法を徹底解説
続きを見る
まとめ:大学中退後は公務員と民間企業どっちがいいの?【5つのチェックポイントを徹底解説】
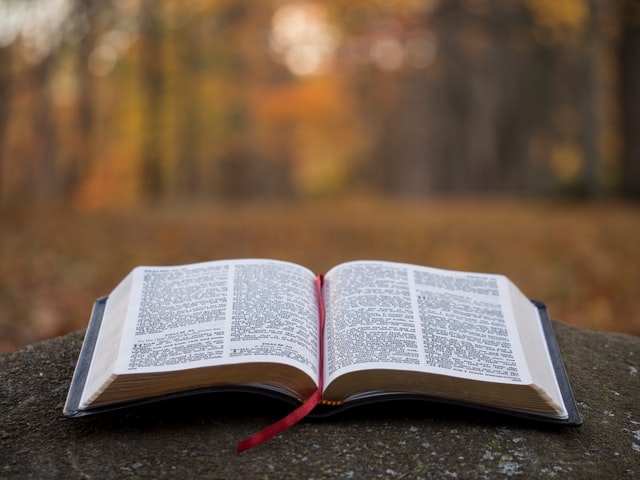
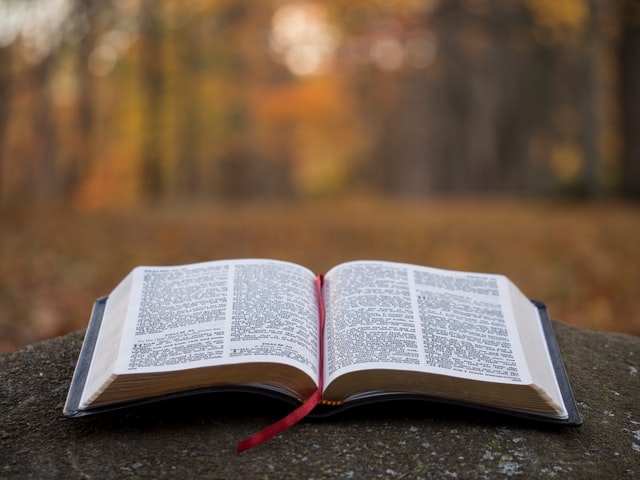
この記事はそろそろ終了となります。ここまでの内容を振り返ります。
大学中退後に公務員を選ばなかった3つの理由
- 大学中退しても稼ぎたいという野心があったから
- 専門的なスキルが身につかないように思えたから
- 都内在住なので仕事の選択肢がたくさんあったから
大学中退しても稼ぎたいという野心があったから
公務員を選ばなかった最大の理由。大学中退して公務員になっても出世はできない。そして安定しているけど少し年収低め。大学中退しても稼ぎたいと思うなら公務員になってはだめだ。
専門的なスキルが身につかないように思えたから
大学中退というハンデに勝つ為に専門的なスキルを身につけることが必要不可欠。しかし、公務員はどんな仕事をしているのか見えなかった。実際には専門知識を身につけることは難しい。(数年おきに様々な現場や部署を転々と異動するのが一般的)
都内在住なので仕事の選択肢がたくさんあったから
首都圏に通えるなら民間企業は星の数ほどある。大学中退だと可能性はグッと減るがそれでも必ずチャンスはある。公務員に限定するとむしろ可能性を狭めることになる。
大学中退後に公務員を考える人が知っておくべき事実を3つ
- 公務員は学歴が重視され、大学中退(高卒)は出世は難しい
- 仕事が楽で毎日定時で帰宅なんかではない(そんな仕事はごく一部)
- 数年後ごとに異動があり、やりたい仕事を選ぶことは基本的にはできない
公務員は学歴が重視され、大学中退(高卒)は出世は難しい
余り知られていないと思うけど公務員は学歴重視。大学中退者が公務員になると「大学中退という烙印」を一生背負うことになる。出世はできないので、頑張れば何とかなるだろう、などと思っていたら痛い目を見る。
仕事が楽で毎日定時で帰宅なんかではない(そんな仕事はごく一部)
私も含めて多くの人が「公務員は定時上がりで楽な仕事」と思っている。実際そんなことはない。嫌な仕こともたくさんあるだろうし、国や地方公共団体の仕事ということでミスができないとうプレッシャーもある。楽そうだからで公務員になると後悔することになる。
数年後ごとに異動があり、やりたい仕事を選ぶことはできない
そもそも自分がやりたい仕事、自分が積み上げたいキャリアを積む、という考え方ではない。公務員は、国や地方公共団体の為に働きたいというベースがないと成り立たないだろう。仕事にやりがいを求める人は向かない可能性が高い。
最後に。
私は公務員という仕事を否定しているのではありません。
公務員になった親族たちは、公務員を一生涯の仕事として選び、国や都道府県のために働くという高い志を持っています。
「楽そうだから」、「安定していそうだから」、そんな安易な考え方で公務員になるのが良くないと言っているのです。
「大学中退後の仕事や人生に不安があるから、安定したイメージのある公務員を選ぶ」は問題の解決になっていないのです。
公務員の仕事そのものに興味がありやりたいのであれば、もちろん公務員を目指すべきで、それを大学中退の不安と結びつけているとしたらそれは間違っていると思うのです。
大学中退後の仕事や人生に不安があるのであれば、それをその不安を解消する為に情報を集めて行動をすべきです。
本ブログでは大学中退後の人生をどうやって生きていくのかの情報を発信しています。
ここにまず最初に読んでもらいたい記事を再掲します。大学中退にまつわる不安が少しでも解消され、今後の人生を生きるヒントになればと思っています。
最初に読んでもらいたい記事
-



大学中退経験者が就職エージェントのすべてを徹底解説【就職成功への全12のポイント】
続きを見る
-



大学中退後の就職を乗り越える【中退経験者が語るベストアンサー】
続きを見る
-



【大学中退者がエンジニアを目指す】中退者にとってベストな方法を徹底解説
続きを見る
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
